コーチングクリニック2018年10月号に特集記事が掲載されました
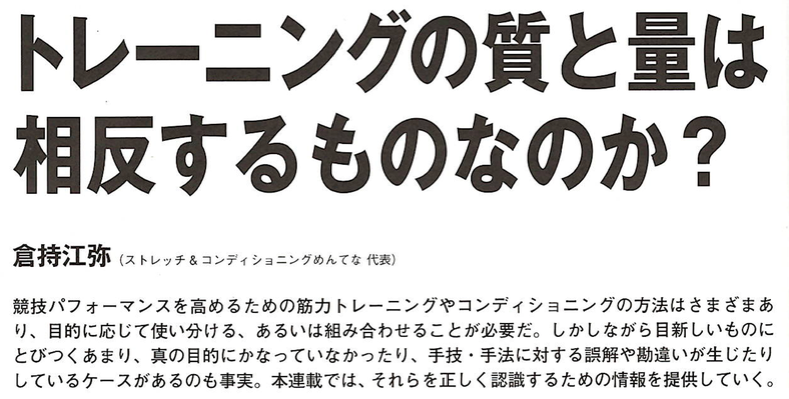
スポーツに携わるすべての人のためのコーチング&スポーツ科学情報誌「コーチングクリニック」2018年10月号に倉持が執筆した記事が掲載されました。
題して「トレーニングの質と量は相反するものなのか」。
トレーニング効果を最大限得るためには、原理原則を理解して
トレーニングをしていくことが大切です。
少し専門的な内容ではありますが、興味ある方はぜひご覧ください。
トレーニングの3つの基本原則
適切なトレーニング効果を得ることや、怪我を引き起こさないためにも
以下にあげる3つの基本原則を考慮しておく必要があります。
(引用:ストレングストレーニング&コンディショニング第三版)
特異性の原則
その目的に合わせたトレーニング種目を選択することで、正しい適応を得ることができます。
例えば、胸を鍛えたければ大胸筋を鍛えるベンチプレスをやる、瞬発力を鍛えたければパワークリーンなどの種目をやるといった感じです。
当たり前といえば当たり前なのですが、目的と種目があっていなければ
いくら頑張っても効果を期待できません。
世間で流行っているからといって、ただやればいいというわけではないんです。
過負荷の原則
人間の体は成長するので、成長に合わせて負荷をあげていきましょうね、ということです。
正しい刺激を与えなければ人間は成長しません。
いつまでも同じ負荷と同じ種目を続けている方をよく見かけますが、
果たしてそれで成長を感じているのか。
もし成長を感じていないようであれば負荷が適切でないということになります。
漸進性の原則
選手のトレーニング状況に合わせて段階的に負荷をあげていくことです。
基本的にトレーニングプログラムは半年や一年など長期的に計画をしていくので、
段階的な負荷コントロールは適応を促しやすくなります。
プログラムを構成する要素
これらの基本原則に基づいて、以下の7つの要素をコントロールすることで
トレーニングプログラムを作成していきます。
●ニーズ分析
●エクササイズの選択
●トレーニング頻度
●エクササイズの順序
●トレーニング負荷と反復回数
●トレーニング量
●休息時間
個別的にそれぞれのプログラム変数をコントロールするのですが、
目的を明確にしておかないと曖昧なプログラムになることがわかると思います。
本稿の内容
記事の詳しい中身は割愛させていただきますが、トレーニング指導をしていく中で
よくある質問に対する答えのような形で書かせていただきました。
主なテーマは、
●トレーニングおける正しいフォームとは
●がむしゃらに頑張ることの意味
●10回×3セットにこだわる理由
●目的にあったエクササイズを選択するために
●トレーニングの質と量は相反するものなのか
というないようになっています。
結局、トレーニング効果をあげるためには量をこなさないといけませんし、
その中で質にこだわるようになってきます。
これは時期によっても変わってくるものであり、量質転化という表現で
説明するとわかりやすいかもしれません。
一つのことを盲目的に行っていくと得られる効果も頭打ちしてしまうので、
自分の目的を理解して体に刺激を与えていきましょう。
今回の特集では今話題の筋膜に関するアプローチ方法なども
紹介されています。
ご興味ありましたら、ぜひご覧ください。
投稿者プロフィール
- 東京都府中市のコンディショニングサロンめんてな代表の倉持です。体のゆがみを整えて、楽に動ける体作りをサポートします。
最新の投稿
 足2025年10月7日足のむくみ解消に効く運動は?つま先立ち(カーフレイズ)とスクワットの効果を比較!
足2025年10月7日足のむくみ解消に効く運動は?つま先立ち(カーフレイズ)とスクワットの効果を比較! 股関節2025年10月2日ヨガやストレッチで股関節を痛めないために知っておきたい3つのポイント
股関節2025年10月2日ヨガやストレッチで股関節を痛めないために知っておきたい3つのポイント 姿勢2025年10月1日寝起きの股関節痛はなぜ起こる?寝る姿勢との深い関係と改善法
姿勢2025年10月1日寝起きの股関節痛はなぜ起こる?寝る姿勢との深い関係と改善法 トレーナー活動2025年8月30日スーパーよさこい2025にトレーナーブースを出展
トレーナー活動2025年8月30日スーパーよさこい2025にトレーナーブースを出展
初の著書|太鼓打ちのための身体の整え方 〜呼吸・体幹編〜
打ち込む力を引き出す!太鼓打ちのための身体の整え方
〜呼吸・体幹編〜
を電子書籍にて上梓しました。
”太鼓打ちのための”という表現になっていますが、野球やテニスといったオーバーヘッド種目、音楽をされている方など身体を使うすべての方に参考になる内容になっています。
これまで様々なチームで指導をしてきましたが、いいパフォーマンスを発揮するためには呼吸や体幹の動きを整えていくことが最優先なのではないか、という結論にたどり着きました。
いかに呼吸を整えることが大切か、体幹の動きを適切なものにするためにはどんなことが必要か、それらを一冊にまとめたものが本書籍になります。
ただストレッチやマッサージ、筋トレをしているだけでは身体を変えることはできません。
その前提としての呼吸の最適化であったり、体幹の動きの最適化をしていくことで、トレーニングの効果もさらに高まってきます。
「腰を痛めることなく動き続けたい」
「呼吸が浅いのをなんとかしたい」
「もっといいパフォーマンスをしたい」
という方におすすめの一冊です。




